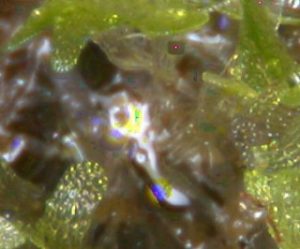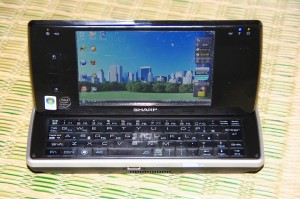このニュースを聞いて、1つの時代が終わったと感じました。
私は、高校時代から計算機のアルゴリズムにのめりこみ、現在でも、独学ながら、サンデープログラマとして、細々とコードを書くことを趣味としています。
大学のころに、APPLEIIを知り、欲しいと思いながら、確か当時20万円を超える価格に、指をくわえて眺めていたのを思い出します。代わりに、シャープのポケットコンピュータを買ってBASICを勉強したものです。
APPLEは、そこから、Lisa→Macintoshを発売してきました。私見ながら、Microsoftは、それを参考に、Windowsを開発したように思えます。私は、appleの思想そのものは好きなのですが、世界がclosedなのが嫌いです。もっと、openであれば、apple信者になっていたでしょう。もちろん、Microsoftも好きではありません。IEなどを強制して使わせようとするところが嫌いです。まあ、だいぶんましになってきましたが。
コンピュータというのは、ユーザーがやりたいことを簡単に自由にできる。好きなアプリケーションを他と競合せず(ハードウェア的に競合するものは仕方がないですが)に使える。
というのが理想です。
理想に近いのが、Linux ですが、なにせ、アプリケーションが少なすぎて、自分がしたいことができないので、バーチャル環境で試用したぐらいです。